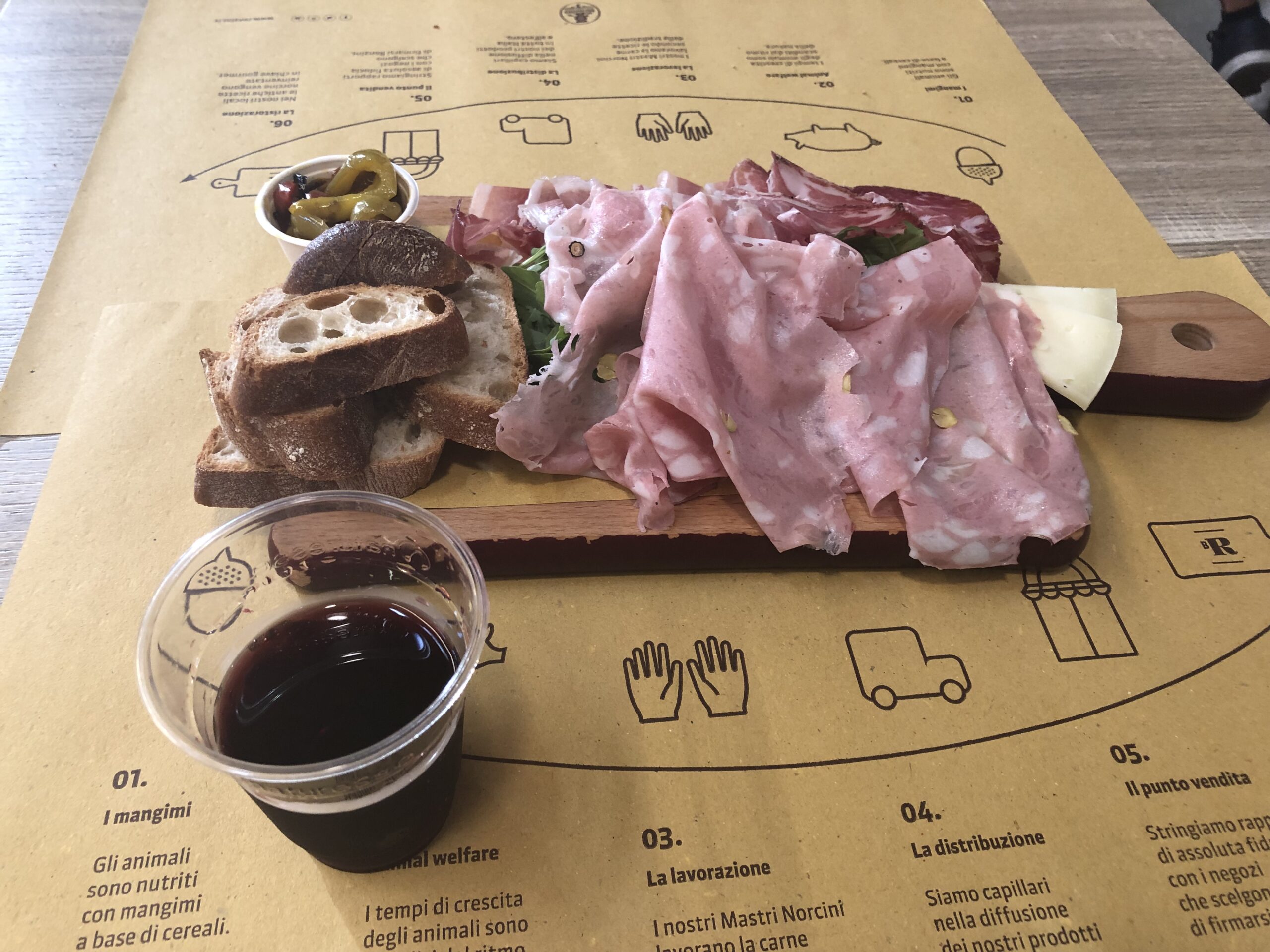<一日目>
今回は、昨年の5月に続き、福井を訪問します。小松空港から出発し、最初は、NHKの「光る君へ」で紫式部が使っていた、武生の越前和紙の里に向かいます。初めに、そこの紙祖神である岡太(おかもと)神社を目指します。後ほど気がついたのですが、ここは岡太(おかふと)神社で、全くの別物。紛らわしいですね。しかし、この地は栗田部地区といい、26代継体天皇が潜龍(即位までの長期間在郷)した歴史有る地区で、この神社は、治水事業の安全を祈願し、476年に創建した由緒有る神社です。そのせいもあってか、建物の細工も手が込んでいます。但し、残念ながら、雪囲いで全容は見えません。本殿は高台に有り、一帯の街並みが、よく見えます。

一の鳥居

(神社境内)


奥に本殿


遠くに街並み
街の中心部にある「紙の文化博物館」に立ち寄ります。ここでは、越前和紙発祥の伝説や歴史が解説されるとともに、美しい手の込んだ和紙の見本が数多く展示されています(展示は残念ながら撮影禁止)。


博物館の前から「和紙の里通り」が始りますが、紙すきの実演を見るため、「卯立の工芸館」に入ってみます。ここは、全国で唯一、工程を一つの工房で再現しているそうです。但し、原料の楮(こうぞ)、三椏(みつまた)は、茨城県等から調達しています。工程は、原料の乾燥した木の皮を釜で煮る→漂白しちり等を取った後、棒で1本の繊維まで打解(重い木の棒で長時間叩きます!)→繊維の入ったすき槽に、トロロアオイの根からとった粘液を入れ、すく→均一に力を加え脱水→乾燥、です。担当の方から、実演も混ぜながら、詳細に説明頂きました。






次は、五箇地区に紙すきの業を伝えた「川上御前」を祀る岡太(おかもと)神社・大瀧神社に向かいます。日本の紙幣は、国立印刷局王子工場から始まり、越前の紙すき職人と用紙開発を進め、世界一の透かし技術を確立したとのこと。そこにはかつて岡太神社の分社もあったそうです。神社の社屋は、拝殿と本殿が一体化し、屋根は独特で、日本一複雑な形状(地元のパンフレットでは)をしています。





拝殿(右)

昼食は、地元の武生製麺が、そばの栽培、製粉、つゆ造りまで、全てを一貫して行っている「越前そばの里」で頂くこととします。人気№2のたけふセットにしました。ちなみに№1は、福井セットで、おろしそばの代わりに、ソースカツ丼です。ここは、観光客だけでなく、地元の人も大勢来ています。




おろしそば・焼き鯖寿司
天ぷら・そば豆腐
水ようかん
越前には、南北朝の時代、刀匠千代鶴国安が、作刀のかたわら鎌を作ったことに始る「越前打刃物」があります。食事の後、越前打刃物の共同工房である「タケフナイフビレッジ」に立ち寄ります。次は、敦賀に向かいます。

(工房)


(売店)

敦賀港を囲むように金ケ崎緑地が整備され、その周囲に歴史有る建物が並んでいます。ところが、一帯は全て定休日が水曜日。残念ながら、どこにも入れませんでした。調査不足ですね。敦賀赤レンガ倉庫では、翌日から9月2日まで「かいじゅうステップSDGs大作戦 in敦賀赤レンガ倉庫」が開催されるようで、PR動画を作成していました。

(杉原千畝が発給した
ビザでユダヤ人が
上陸した史実を紹介)

(左は休憩所)


(旧敦賀港駅舎)


気を取り直し、神社仏閣を巡ります。最初は近くの金崎宮(かねがさきぐう)です。ここは南北朝の戦いで金ケ崎城に籠城し、非業の死をとげた、後醍醐天皇の2人の皇子、尊良親王、恒良親王を祀る神社です。尊良親王が永年思いを寄せた姫とめでたく結ばれたことから、恋の宮として有名です。また、「金ケ崎の退き口」の際、お市の方が、両端をひもで結んだ小豆袋を兄の織田信長に届けたことで、窮地を脱したという逸話に因み、「難関突破守」も置かれています。

(金崎宮の入口)


(恋の宮!)

次は、越前国一宮の氣比(けひ)神社です。ここは、古事記や日本書紀にも記述が有り、主祭神の氣比の大神は、2000年以上前に、ここに降臨したと言われています。境内の建物は空襲で焼失したそうですが、火災を免れた朱色の大鳥居は、日本三大木造大鳥居(他は、春日大社と厳島神社)と言われています。境内には、702年に社殿建立の際に湧き出したという神水(名称は長命水、飲んでみました)や、南北朝争乱の1336年に宮司氣比氏治が南朝後醍醐天皇を奉じ氣比大明神の神旗を掲げたと云う旗掲の松(落雷で焼け、旧松根として残る)があります。またこの神社は、奥の細道の最後の方で松尾芭蕉が訪れています。






(奥の細道の風景地)
宿泊先であるマンテンホテルに行く前に、日本三大松原(他は、美保の松原と虹の松原)である氣比の松原に立ち寄ります。ホテルは駅の直ぐ近くにあります。新幹線が開通したことも有り、駅舎は真新しいです。




夕食はホテルの方の勧めも有り、まるさん屋に入ります。このお店は、下が魚介系の土産物屋で、2階が昼から夜までずうっと開いていて、寿司から鍋から定食から何でもある居酒屋です。地の物、季節の物を、色々頼んでみました。地元の人も訪れるおいしい店でした。これで1日目は終了です。